これから先の20年で、人間の仕事は半分に!?
AIの普及でなくなる仕事と、残っていく仕事
2017.07.06
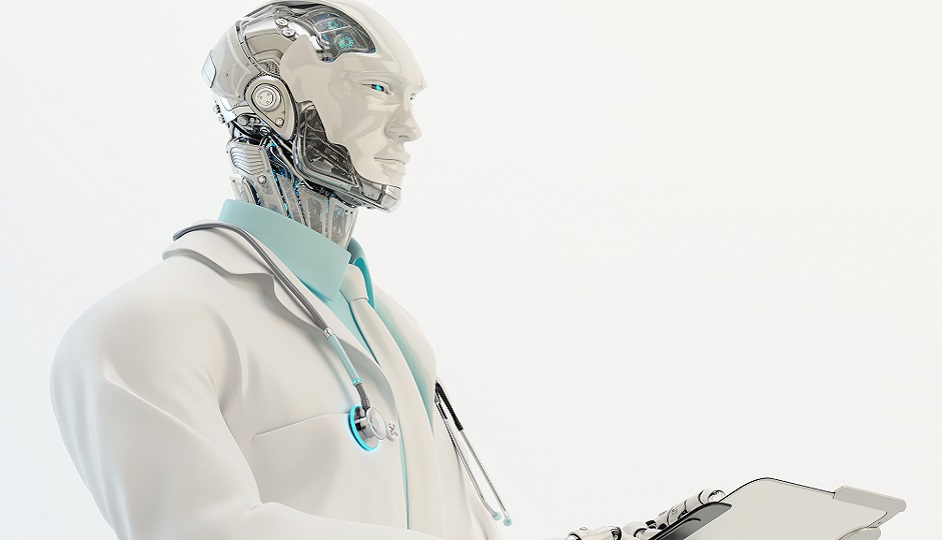
「人の仕事が奪われる」と言われるほど、進化を続けるAI(人工知能)。囲碁や将棋だけでなく、作曲や、小説を書いたりとどんどん器用になっており、今後何ができるようになるのでしょうか? AIの進化によってなくなる仕事・残る仕事を考えてみます。
AIの普及で、人が必要なくなるのはどこまで?
AIがこれまでの機械と違っているのは、自分で学ぶ機能をもっている、ということです。たとえば「囲碁で強くなる」という目的を設定すれば、AIは対戦する中で相手に勝つための戦法を自動的に学んでいきます。これまでの機械はプログラムされたことを実行するだけでしたが、AIは人間のように学習し、「自ら成長していく」のです。
しかも、一つひとつの作業スピードは人間が到底追いつかない速さなので、成長していくスピードも圧倒的。その結果、最近では「これから先の10〜20年ほどで、アメリカのすべての雇用者の約47%が機械になる」という論文も出ているほどです。現在でもアメリカのがんセンターでは、AIが膨大な医療データを分析して、患者の治療計画を提案することがあるようです。よく言われる「AIが人間の仕事を奪う未来」も、決して冗談ではすまなくなってきました。
警備員や運転手など、ルール化できる仕事は奪われる?
では、どんな仕事がAIに奪われてしまうのでしょうか? 可能性が高いのは、「決められたルールに基づいて動く仕事」です。たとえば事務や会計、契約書をつくる専門家やデータ分析のプロのように、一定のルールの中でデータを集めて計算したり、まとめたりする仕事は、AIの得意分野です。
また、警備員や運転手もAIに代わる可能性が高いでしょう。警備員は決められたルールの中で安全を守る仕事ですが、それをAIに任せれば、想定外のでき事への対応は難しくなるものの、人が危険を負う必要がなくなります。運転手も同様で、バスやタクシーの動きは、ある程度はパターン化することができるものです。世界では今、AIによる自動運転の研究が進んでおり、やがては自動車の運転にも人が関わらなくなるかもしれません。
なくならないのは対面での会話で、ルール化しにくい仕事
反対に、どんな仕事が残るでしょうか。「ポイントはルール化しにくいもの」、そして「人と人とのコミュニケーションで成り立つもの」です。

もっとも分りやすいのが、お客さんと一対一で向き合い、コミュニケーションを取る職業でしょう。患者さんからの相談を受けて解決策を一緒に考える心理カウンセラー、宿泊客の様子に気を配り、想定外のルールに収まらないお願いにも答えるホテルスタッフの仕事、要望をくみ取り商品を紹介するセールスマンの仕事には、豊かなコミュニケーションが欠かせません。しかし、会話というものは、人により千差万別なのでルール化するのが難しいのです。
また、「人と話している」という安心感は大きく、もし同じ話をしていても、相手が機械だと不安を抱く人もいるかもしれません。そのことから、独自のスキルが必要な販売や接客といった対面で行なうサービス業のニーズは、AIの普及によって失われにくいものだといわれています。
まとめ
今後数十年でAIはさらに進化し、私たちの仕事環境は大きく変わるでしょう。ただその中でも、独自の技術をもったサービス業、対面の接客はなくならないはず。であれば、今からきちんとそのスキルを高めて、未来に備えることが大切ではないでしょうか。



